相続・遺言
タイの相続・遺言に関する法律は、日本の民法にあたる民商法の第6編に定められています。
相続や遺言に関する法律上の定め、手続き方法については、相続・遺言を解説・サポートする専門サイト「相続・遺言ラボ」をご参照ください。
なお、当サイトに掲載していました相続、遺言に関するコンテンツはすべて「相続・遺言ラボ」に移転しましたのでご了承ください。
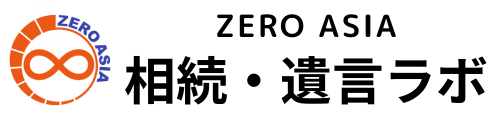
民商法第6編 相続
第1章 総則
第1節 相続財産の相続
第2節 相続人
第3節 相続廃除
第4節 相続放棄
第2章 法定相続権
第1節 総則
第2節 相続順位
第3節 法定相続分
第1款 血族
第2款 配偶者
第4節 代襲相続
第3章 遺言
第1節 総則
第2節 遺言の方式
第3節 遺言の効力および解釈
第4節 遺言による財産管理後見人の指定
第5節 遺言の撤回および失効
第6節 遺言の無効
第4章 遺産分割方法
第1節 相続執行者
第2節 相続財産の換価および債務弁済
第3節 遺産分割
